
最初は、よくある成功談かと思ったのですが、エッセイ風に書かれていたのと、そこから伝わるお人柄にも結構惹かれました。「ツイてない人間って、自分のことを「ツイてない人間だ」と思っているだけなんですよ。ツイてる人間とツイてない人間の違いとは、たったそれだけのことなんです」とあるように、全編を通してポジティブな人だなぁ・・と。
また、合わない人と会わないためには、少しお金が必要だから働く、とも書かれています。意味は少し違いますが、チャップリンの「幸せには、想像力と、ほんの少しのお金があればいい」というセリフを連想してしまいました。(^^)
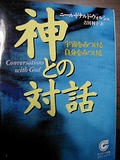
副題として「宇宙をみつける 自分をみつける」とあります。著者と神との対話形式で書かれている本です。著者の哲学が述べられていると理解しました。そして、「神は観察者であって、創造者ではない」と語る著者にとっての神とは、自己の生命の根源そのものと、私は理解しました。
そういえば、他の色々なフレーズで、思い出す人や言葉がたくさんありました。 「人間」感については、桂枝雀さんの言葉:「人間はもともと一つの餅みたいなもんです。それぞれが小餅。こねていないと硬くなる。もともと一つやから、硬くなったら、もう一回あっためて、一つにまとめて臼でついたらいいんです・・笑いもそれです」というのもそうです。
読後感としては、この本の最後にある田口ランディさんの解説とほぼ同感といえます。私の場合、断定的な物言いよりも、こちらに考える余地を残してくれるような、たとえば児童文学やエッセイ等から著者のメッセージを自分の地図の中に取りこんで想像するような読み方の方が、好きではあります。だからニールさん、願わくば、神との対話表現も寸止めにして欲しかったなぁ・・と。(^^;
しかし、田口さんが著者にインタビューした際のコメントとして、以下のような言葉を読んだときには、ちょっとほっとしました。・・「もしそれがあなたにとって価値のないものだと感じるなら、その源がなんであろうと、そんなものは捨ててしまいなさいと言いたいのです。もし、意味があれば、その源を自分の側におきなさい。アイディアがどこからやって来たのか、ではなく、アイディアそのものの価値について語り合おうではありませんか」と。確かに、語られているアイディアそのものについて、つまり、それぞれの持つ哲学について話すうちに、様々な共通点を見出せるであろうことは、純粋に嬉しいことだろうと思います。
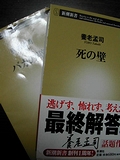
「ばかの壁」も後から読みましたが、私は「死の壁」の方が納得するところが多かったです。私の読書不足ですが、養老さんには仏教哲学の思考がベースにあることが、この本からよりはっきりと分かった気がします。「生」と「死」について色々な角度から話したことを本にしたものですが、いつも死体を見つめていた解剖学者として語る「死」について、「人」についての言葉には説得力があります。
命について語るとき、「そこを飛んでいるハエですら『そんなもの、殺したら二度と作れねえよ』という昔のお坊さんの方がよほど簡単に答えることができる。」という一節が分かりやすく伝わります。人間を自然として考えてみると、「他人という取り返しのつかないシステムを壊すということは、実はとりもなおさず自分も所属しているシステムの周辺を壊しているということなのです」と「人間中心主義」の危うさも話しています。これは、先日聴いてきた「環境問題」についての満田久義さんのお話(著書:「環境社会学への招待」朝日新聞社 近刊)と一致していて、納得した一節でもありました。(このお話は、後日別のページに書いてみたいと思っています。)
「意識化することを一つの目標とするのは、学者としては正しい立場なのかもしれません。しかし、私はどこか根本的に見落としているところがあるような気がするのです。言語に絶するというか、どこかで言葉に出来ない領域というのがあるのではないか、あってもいいのではないかと思うのです。」という、言葉に関する一節も納得。言葉が素晴らしい手段であるのは間違いないですが、言葉そのものが生きることそのものも含めて、物事を難しくしているのも実感ですよ・・・ね。(^^;
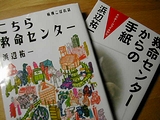
読み終えているのですが、感想はもう少ししたら書きます。 実は息子が読んでいて、本が手元にないものですから・・。(^^;